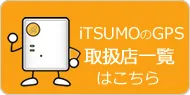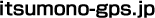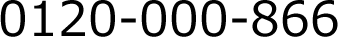かつては街を歩けば子供たちの遊ぶ声が聞こえてきましたが、最近では高齢者の姿が目立つようになり少子高齢化が進んでいると実感します。
さて、街中で認知症の方が徘徊しているのを見かけたことはあるでしょうか?またその方に声をかけた経験があるという方は、まだ少ないのではないでしょうか。
今回は、もしも街中で認知症で徘徊している可能性のある方を見つけたらどうしたらよいのかについて考察していきます。
1.徘徊している方の見分け方・・・
まず見た目で判断できる場合もあります。
例えば、夏なのに冬服を着ているなどの異常な服装の方もあれば、きれいに正装されていて、一見すると全くわからない方など、その方によって徘徊している方の服装は全く異なります。
どう見分けるかはとても難しく、特徴としてはまっすぐ一点だけを見つめて険しい表情で歩いている方が多いという傾向があります。
また、逆に不安そうにキョロキョロと周囲を見回しながらウロウロされていることもあります。
これは、外出してすぐは目的をもってまっすぐ進んでいくのですが、途中で行き先がわからなくなったり忘れたり、見覚えのないところに来て不安になるという心境からこのような行動になることが多いです。
2.声をかけるタイミングと方法・・・
声をかけるタイミングは、不安そうにされているときです。
険しい表情や急ぎ足で歩いている場合は、逆に声をかけるのを控えた方が良いでしょう。
まずは、落ち着いた声で、「こんにちは、大丈夫ですか?」や「どこへ行かれるのですか?」など、優しく声をかけることが重要です。
また、声をかける際には、相手の安全を第一に考え、無理に引き止めたり、急かしたりしないよう注意しましょう。
もし相手が混乱している様子であれば、無理に話を続けるのではなく、周囲の安全を確保しつつ、必要に応じて専門機関や警察に連絡することも検討してください。
3.声をかけた後どうしたら良いのか・・・
会話の中で、徘徊であることを確信されたら迷わず警察に連絡してください。
その際、どちらの方向から歩いてこられたのかなどできるだけ具体的な情報を提供していただけるとご家族につながる可能性が高くなりますのでよろしくお願いします。
本人には、「警察に道を聞いてみましょう」などと警察につなぐことをスムーズに理解してもらえるように話してください。突然目の前に警察の方があらわれて連行されたら誰しも嫌ですから。
あとは警察の方にお任せしてあなたの時間に戻ってください。
4.早期発見・早期保護のためにご協力を
認知症で徘徊し、仮に保護されずに丸1日経過すると、季節にもよりますが生存率が大きく低下します。
5日間保護されないと生存率はほぼゼロになると言われており、とにかく早期の発見・保護が重要です。
認知症で徘徊する方をご家族に持つと、毎日が心臓に悪いことの連続です。救急車やパトカーの音に過剰に反応したり、常に不安が襲い睡眠不足になったり、ストレスから体調を崩すケースもとても多くみられます。
もし、あなたの周囲にそのような悩みを抱えたご家族がいる場合は、まず専門家に相談することを強くおすすめします。一人で抱え込まず適切な支援を受けることが何よりも重要です。
今後も高齢者の増加に伴い、認知症や徘徊される方も増えていく見込みです。また、以前のように認知症になったら家に閉じ込める という対応も見直されつつあり、GPS機器等を活用することで徘徊があっても外出できる環境が整いつつあります。
※例えば、iTSUMO(いつも)をご利用いただいた方の中には、従来は鍵をかけて24間監視していたのをやめ、iTSUMO(いつも)のGPSで見守ることで平穏な日常を取り戻したケースも多くあります。
ただし、iTSUMO(いつも)には安全を守る機能はありません。事故にあう可能性は外出している以上常にあり、道案内の機能もありませんので、ご家族がそこは理解したうえでお使いいただくことが重要です。
もしも、認知症で徘徊している可能性のある方を見つけたら・・・あなたのちょっとした勇気が一人の命を救うだけでなく、そのご家族の未来にも大きな影響を与えることがあります。
声をかけることは勇気のいる行動ですが、その際にはまず警察に連絡し、職務質問をお願いする方法もご検討ください。
早期発見・早期保護のために、ご協力をよろしくお願いいたします。

資格:介護福祉士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級
措置時代から介護業界で働き(アラフィフ)、介護保険制度施行後もずっと介護現場に携わってきている。特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・グループホーム・通所介護(デイサービス)・小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援(ケアプランセンター)・福祉用具貸与での勤務経験を有し、介護事業所の立ち上げに数件参画。
現在は福祉用具の企画コンサルタントとして、新商品の開発などに携わる傍ら、これまでの介護現場の経験をもとに、介護の楽しさややりがいなどを伝えていきたいと考えている。
研修:認知症介護実践者研修・認知症実践介護リーダー研修・認知症対応型サービス事業管理者研修