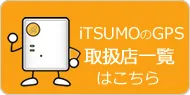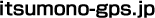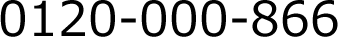新オレンジプランとは、日本政府(関係12省庁)が2015年に策定した 認知症施策推進総合戦略の愛称です。
高齢化が進む中で、認知症の人は今後ますます増加すると見込まれており、社会全体で支える仕組みが必要とされています。
日本政府は従来の施策を見直し、認知症になっても安心して暮らせる地域を目指して、医療・介護だけでなく地域を単位として、家族・本人の尊厳 を守ることを目的に作られたのが「新オレンジプラン」です。
基本的な考え方
新オレンジプランの基本的な考え方としては以下の通りとなります。
・認知症になっても安心して暮らせる社会の実現
・本人の意思の尊重と尊厳の保持
・地域包括ケアシステムとの連携
となっており、認知症になると鍵をかけて閉じ込めるなどの虐待行為が当たり前であったものを、本人の尊厳を守り、地域全体で見守ることができる社会を作り出していくというものです。
7つの柱
 新オレンジプランでは、以下の7つを重点施策としています。
新オレンジプランでは、以下の7つを重点施策としています。
1.普及・啓発
認知症に対する理解を広げ、偏見をなくす取り組み(認知症サポーター養成など)
2.予防
生活習慣病の改善や運動習慣による発症予防・進行抑制
3.医療・介護サービスの提供
早期診断・早期対応、専門医療機関や介護サービス体制の強化
4.若年性認知症への支援
就労や生活の継続支援や介護者への支援
5.家族や介護者の負担を軽減する仕組みづくり
6.徘徊などへの対応(SOSネットワーク整備)
地域全体での見守り体制、警察や自治体との連携、GPS活用など
7.研究開発・産業振興・人材育成
治療法の研究や介護人材の育成
つまり「新オレンジプラン」は、単なる医療・介護政策ではなく、 社会全体で認知症の人を支えるための総合戦略 なんです。
新オレンジプランとiTSUMOの関係
アーバンテックはちょうど2015年から事業を開始しており、認知症施策の一翼を微力ながら担わせていただいております。
ただ、2015年当時はまだ認知症の理解も低く、現代のように当事者の能力の活用はおろか、声を聴くということも十分ではなく、ともすれば過剰な保護が行われることもありました。それでも鍵のかけられた部屋に閉じ込められていた過去と比較すると、対応は改善させてきていたという印象です。
こうして国が方向性を示すことは重要で、2000年に介護保険が施行された当時は想定もできなかった認知症患者の急増や、それに伴う諸課題の解決に、奔走していたという時代ですね。
iTSUMO発売当初ケアマネさんの反応はすこぶる悪く、「機械で見守りなんて・・・」「介護は人がするもの・・・」という声が多く聞かれました。
しかし最前線で介護しているご家族からは「待っていました!」という反応をいただきました。
「新オレンジプラン」が普及していく過程で、認知症への理解、徘徊への理解、徘徊する方の家族の心情の理解なども進み、iTSUMOのGPSが有効であることが徐々に評価されていったという経緯があります。
そいう言う意味ではこの「新オレンジプラン」とiTSUMOは一緒に成長(普及)してきたと言えるのかもしれません。

資格:介護福祉士・介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級
措置時代から介護業界で働き(アラフィフ)、介護保険制度施行後もずっと介護現場に携わってきている。特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・グループホーム・通所介護(デイサービス)・小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援(ケアプランセンター)・福祉用具貸与での勤務経験を有し、介護事業所の立ち上げに数件参画。
現在は福祉用具の企画コンサルタントとして、新商品の開発などに携わる傍ら、これまでの介護現場の経験をもとに、介護の楽しさややりがいなどを伝えていきたいと考えている。
研修:認知症介護実践者研修・認知症実践介護リーダー研修・認知症対応型サービス事業管理者研修