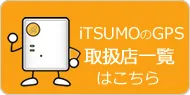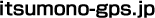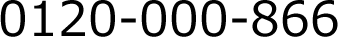見守り対象:お母さま
◎介護保険適用
見守り体制:ご家族
GPSの取り付け位置:普段履きの靴
見守りをされるご家族は都市部のマンションにお住まいで、ご夫婦と小学生のお子さんが1人の3人家族、ご夫婦は共働きという状況下、お母さまは隣町にある実家でお一人暮らしをされています。
転倒骨折→入院退院後に変化が・・・
ある日、お母さまが転倒骨折され、しばらく入院していたのですが、その退院後行動に変化が見え始めてきました。
それまできれい好きで、実家に帰るといつもピカピカだった家が、物が散乱し、異臭もしていました。お母さまの服装もなんだか季節外れの服で、洗濯もしているのか?という汚れ具合、お化粧もされずなんだかボーっとした表情でした。
実はご家族の奥様(娘さん)が介護職で、その様子を見た奥様はすぐに地域包括支援センターに連絡し、要介護認定を受けることに。要介護認定を受けるには主治医の意見書が必要なのですが、それまで病気と無縁だったお母さまはかかりつけの医師もいない状況でした。そこで紹介してもらった医者での診断は「認知症」でした。それに伴い、要介護度も「要支援2」となりました。
将来のことを考えて家族会議を開きましたが、お母さまは住み慣れた家で暮らしたいと・・・。しかしご夫婦は共働きでお子さんもまだ小学生です。
そこでケアマネジャーさんに相談し、在宅介護サービスを利用することで様子を見ることになりました。
早め目に認知症の徘徊対策としてiTSUMO(いつも)を使用開始
徘徊の傾向はありませんでしたが、認知症の進行が早く、どんな症状が出るか予測がつかないこと、ご家族が同居ではなく心配で不安なことから認知症徘徊対策としてiTSUMO(いつも)の使用も開始しました。それからしばらくは、在宅サービスの利用や、ご家族も今までよりも気にかけて訪問したりすることでお母さまの状況も落ち着き、以前のようにきれいな家、きれいな服装になっていました。
そんなある日、買い物に出かけたお母さまが「散歩」エリアから「出た」という通知が奥様(娘さん)に届きました。(iTSUMO(いつも)のGPS機能で普段の行動半径を「散歩エリア」として設定でき、そこから出るとメールやプッシュ通知が届き仕組みです)
奥様(娘さん)がスマホで確認すると、普段よりも遠いところを指しています。しかも時間を追うごとに遠くへ行っているようでした。
そこで、位置情報をもとにお迎えに行きました。移動経路もわかるので、少し先回りをして偶然を装い出会います。するとお母さまの表情が明るくなり「良かったー」と安心されました。どうやら自宅に帰る途中で迷ってしまい、わからないまま直進してしまったようです。
上記のように、GPSの機能をうまく使うことで、日頃は介護サービスにお任せし、緊急時などはご家族が対応することで、役割を分担でき、ご家族も今まで通りの生活を継続しながらお母さまも在宅生活ができています。もちろん今後、状態(ADL)は変化することはあると思いますが、いざという時の安心感が高まったというお声をいただきました。
アーバンテックスタッフから
GPS機能を上手に活用することで、「見守り」という実は一番難しい介護を機械にある程度任せることができる。ただし「ある程度」です。
行き過ぎた見守りは「監視」になりますし、見守らないことは「虐待」になる可能性もあります。
まずは「全員が肩に力を入れずに生活できる状況ってどんな感じ?」ということを前提に検討されるとうまくいくことが多いように思います。