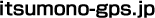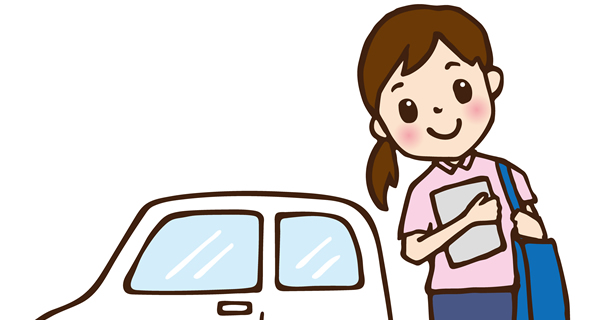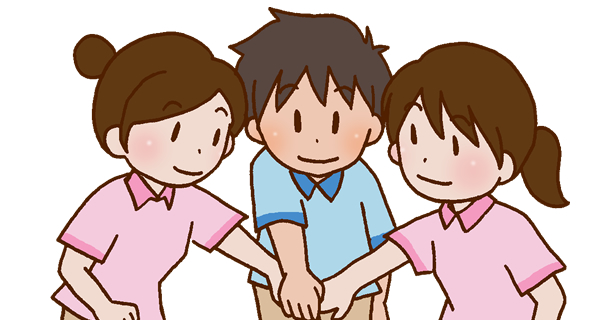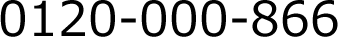★奈良市K様 女性70代 要介護1
◎介護保険適用
見守り体制:息子さま
GPSの取り付け位置:自転車
iTSUMOご利用者の中には、自転車に取り付ける方も結構おられます。いつも外出されるときに持って出ていただける可能性が高い場所が正解ですので。
さて、この方も必ず「自転車」に乗って出掛けます。
そこで、ご家族と相談するとやはり自転車に取り付けることで決まったのですが、少し嫌な予感がしていました。
自転車が「電動自転車」だったのです。
これ・・・ひょっとして・・・すごく遠い所に行ってしまうかも・・・
2週間後、その嫌な予感が的中してしまいました。
その日はご家族も仕事が遅くまであり、夜の10時頃ようやく事態に気付きました。
iTSUMOを位置検索すると、ご本人は自宅からかなり離れた山の方へゆっくりと動いていました。
この時、
① すでに「電動自転車」の充電が切れていた。
② 夕方に、一般の方から通報があり早いタイミングで「警察」が動いていた。
ということでした。
結果、ご家族が警察に連絡をすると、すでに無事保護されていました。
今後は「電動自転車」を「自転車」に検討されるそうです。
実は、通報してくださった方が警察に通報して、到着を待っているときに、電話をしている隙にまたどこかへ行ってしまったのだそうです。
そこで、警察はもう一度ご本人を探さないといけなくなり、人員を増やして探してくださったそうです。
ともかく無事保護できてよかったです。
徘徊されている方が「ケガをしていたり」「裸足だったり」「挙動不審だったり」すれば目印になりますが、普通は特に見た目変わらない方がほとんどで、なかなか声を掛けるのは難しいというのが現実です。
ちなみに警察は、以下のことを注意しているそうなのでぜひ皆さんも参考にしてみてください。
・深夜や早朝に高齢者が不審な動きをしていないか
・人がいない場所で高齢者が歩いていないか
・季節にあった服装をしているか(夏に長袖など)
・天気に適した服装をしているか(雨の日に傘をさしていない)
・手足や顔面にケガをしていないか(転倒される方が多い)
・左右ちがう靴をはいていないか
・衣服や所持品に名前が書いていないか
もし、徘徊されていると思って声を掛けてもそこからがまた難しくて・・・・・
知らない人が急に声をかけると「自分は道に迷っていない」「自分は認知症じゃない」と返答される方が多く、後を付けていくと怒られたりします。
そんな時は、迷わず警察に連絡してください。保護願が出ている方であればすぐに保護してもらえます。
しかし、声をかけるのはためらわれるという方も多いと思いますので、その場合は、服装や雰囲気どちらの方角に向かったなどできるだけ詳細な情報を警察までお伝えください。
これからの季節、外を歩くのが気持ちいいですから当然「徘徊」も増えます。皆さんも街を歩かれる際は、上記心がけてみてください。